当時、ロンドンの市民達は、かって古代ローマ帝国の軍団が築いた
城壁(シティ・ウォール)の内側に住んでいた。ローマ軍団が去って千
年の年月が過ぎていたから、城壁そのものは、あちこちで崩れ、完全
な防備の城壁ではなかったが、それでも市民が団結をすれば、外敵
を防ぐには十分な役割を果たしていた。
ところが、シティを囲む城壁の東の跡地にウィリアム王が築いた『ロ
ンドン塔』は、東半分は城壁の外に張り出し、外部からの攻勢に睨み
を利かしていたが、西半分は、どんと市内に食込んでいたからである。
シティの中に城が出来てしまったのである。
ロンドン商人の貨物は、テームズ河が動脈となって集散している。
フランダースの織物・銀器・フランスの家具・小麦・葡萄酒・青果物・
北欧の干魚類・遥か東方オリエント諸国の珍味、宝石貴金属、香料
・・・それらは全てロンドン塔の下で検問を受けねばならなくなった。
船も荷物も、倉庫も邸宅も、物見櫓からいつでも見張られていると
いう圧迫感があった。
たくましい馬を連ねて、槍騎兵達が市内外の巡視に当たっていた。
市内での反乱の気配は見る見る萎んでいった。
大商人達は、いつの世でも権力に媚を売る。それが商いの流れで
ある。彼等はウィリアム新王のこれからの力と、生き残っているアン
グロサクソン大貴族達のそれとを天秤にかけて、さりげなくひそひそ
と談合をしていた。
ウォルターは、ウィリアム王がイングランド侵攻の野望を持ちはじめ
た少年の頃から、ノルマンディーと貿易をしていたシティの商人の何
人かと密かに接触をして、すでに情報網に取り込んでいた。
なかでもワイン商のグラントはウォルターの密命によって、二十年も
前からシティに来て小さな店を開き、今では店員十数名を使う中堅の
商人として信用があった。イングランドでは葡萄が実らないので、ワイ
ンはすべてフランスやドイツからの輸入である。グラントは同業者とも
そつなく付き合いつつ、よいワインを貴族達に売り込み、二十年の間
に彼等の御用商人としての確固たる信用を得ていた。
イングランド国内に散らばっているウォルター麾下の間者達の組頭
であった。
間者達が、番頭・執事・料理人・侍女としてシティの有力商人や豪族
の中に深く食込んで、重厚な情報蒐集網を完成していることは、ウィリ
アム王とウォルターの二人の他は、重臣達はもとより間者達相互の間
でも全く知らない。
シティの商人のなかでもとりわけ信望の厚いアンスガーという商人が
いた。
ヘイスティングズの戦いでハロルド伯が戦死し、エドウィン伯やモルカ
ー伯が北へ引き揚げると、シティの自衛はアンスガーの指揮下にあっ
た。万一の場合には市民が武器をもって、シティ・ウォールの中で戦う
相談もできていた。
ワイン商のグラントはウォルターへ逐一シティの状況を報告していた。
ウィリアム王は、ヘイスティングズの戦いの後、アンスガーに密使を出
し、「われ等に楯突かねば、商業は保障する」旨伝え、回答を求めて
いた。
アンスガーは自らは「諾」とも「否」とも密使には即答せず、ウィリアム
王の真意を、商工会幹部数名を王の許に伺わせ直接確かめさせる方
法をとった。
ロンドン・シティの商人の強かさには、歴史と血の積み重ねがある。
機を見るに敏でありながら、一方的な賭けはしない。両天秤にかける
か、あるいは、どこかで危険は分散され、逃げ道が用意されていた。
アンスガーを会頭とするロンドン商人の結論は明快であった。
シティの商人達は忠誠心の証として多額の金銀を差しだし、新王よ
り王室特許状(ロイヤル・チャーター)を交付してもらい、自分達が永
年にわたって築き上げた権益を守る選択をとった。
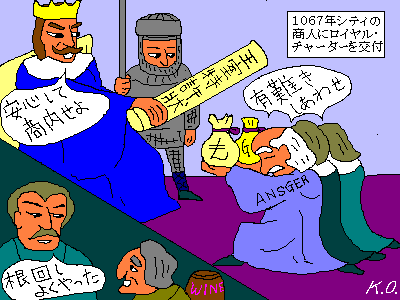
新王の強かさに賭け、もっと儲けようと蠢動したのではない。あくま
でも身を護り、特権を維持するためにはどうしたらよいかというのが価
値判断の基準にあった。hedgeの思想である。
余談になるが、日本では英語の”hedge”の行為に対応する適当な
邦訳がない。hedgeは、もともと垣根であるが障壁・防衛策さらには危
険分散のために両天秤に賭けることまで意味が広がる。保険の中心
地シティでは、昔から危険分散、両天秤の思想が生活の知恵として根
付いていた。
経世済民の政治を行うには、ウィリアム王もまたシティの機能と協力
を必要とした。
グラントはロンドン商人達の談合にうまく立ち回った。王は、アンスガ
ーを代表とするシティの大商人や海運業者達に王室特許状を交付し、
彼等を安堵させ、経済網を掌中に収めた。
「グレート・ブリテン・・・この大国の頭がロンドンだとすれば、テームズ
河畔のロンドン塔は、その喉元を締め付ける首輪だな、ウォルター」
「左様でございます。首輪というよりも、刃を突き付けたようなものです。
先般は『イングランドの鍵』ドーバー城を無血占領しました。我らノルマ
ン軍団の司令塔ともいうべきロンドン塔が完成した今、アングロサクソ
ン貴族の反乱もすぐには起こりますまい」
「次の手は何かな?」
「留守をしているノルマンディーへの配慮でしょう。フランス王や周辺
の諸候への牽制のために、いったんノルマンディーへ華々しく凱旋す
るとよいでしょう。凱旋のプログラムについて、そろそろ王とお打ち合
せしたいと存じます」
「よかろう。愛しいマチルダにも早く逢いたいものだ」
二人は木の香も新しい会議室へと足を向けた。
第2章 凱旋(1)
「われ国を建つ」目次へ戻る
「見よ、あの彗星を」目次へ戻る
ホームページへ戻る